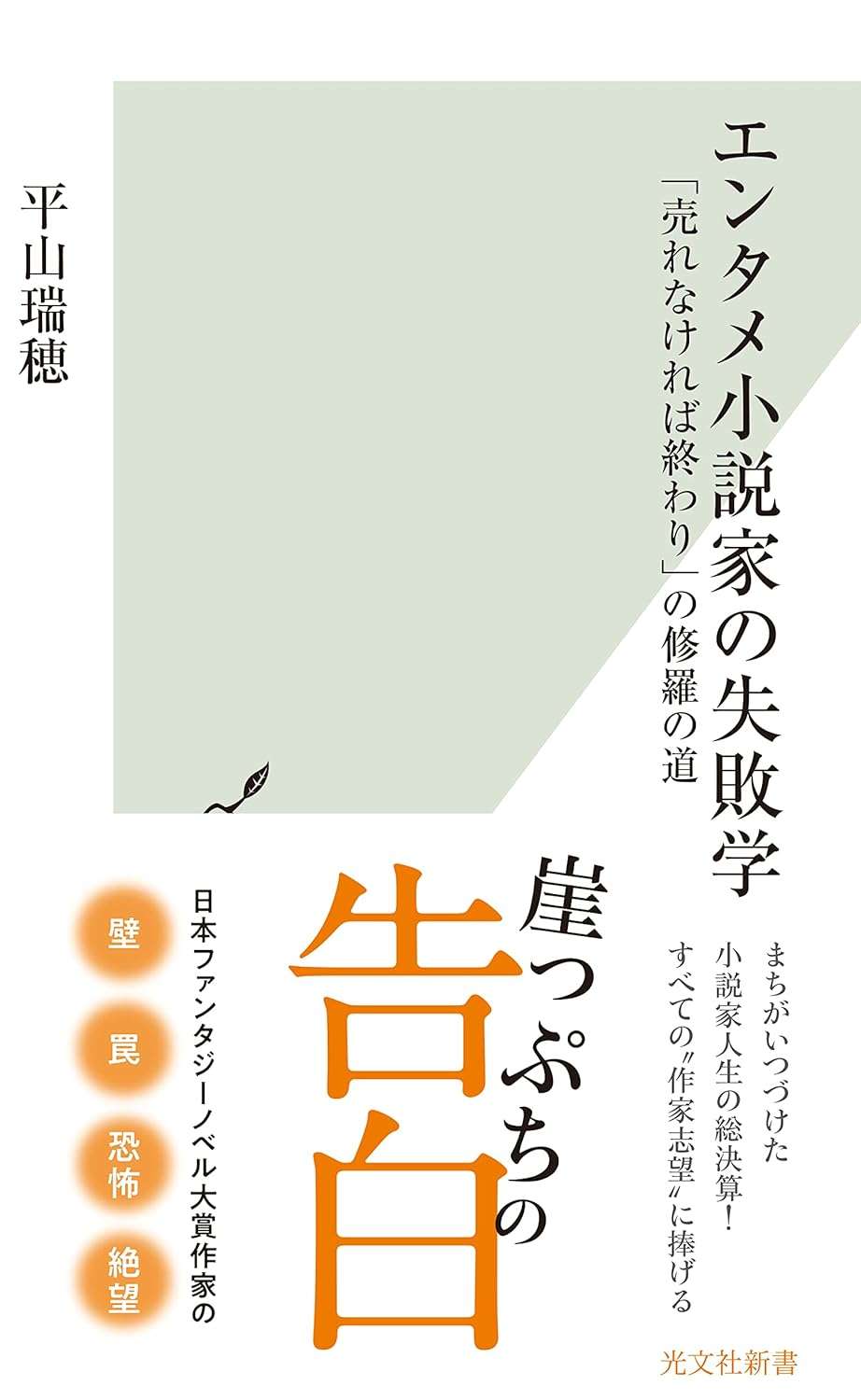
知らない作家だったけど、タイトルに惹かれて手に取った一冊。エンタメ小説家による「失敗の解剖」という珍しい切り口が面白かった。
赤裸々な失敗談の本
失敗学というタイトル通り、著者がこれまで出してきた本の「ここが駄目だった」「こういう理由で失敗した」という話があけっぴろげに書かれている本。こういう自作のダメ出しはあまり表立って目にする機会がないので新鮮だった。
とはいえ最近はTwitterなどでラノベ作家が「この本はうまくいかなかった」といった発信をすることもあるけれど、これだけまとまった形で、しかもエンタメ系作家が「この本は部数が伸びなかった」「重版しなかった」と具体的に語るのは珍しく、そこが読みどころになっている。
しかもしなかった理由やだいたいの部数を生々しく話してくるからまた、なあ……。読んでて「ああ、うん……」という気持ちに何度もなった。
読んでいて面白かったのは、単行本の読者は作家につくけれども、文庫本の読者は作家にはつかずふらっと買っていくというあたり。確かにこれはすごくわかりがあるかも。
単行本って場所は取るわ高いわで一種の嗜好品じみている部分があり、対して文庫は安い(安くない)ので気軽(気軽じゃない)に買える。ふらっと書店に入ったときに単行本サイズのラノベは買えないけれども文庫サイズで新刊平置きされているのは買える(高い)。
そのため、単行本で出る本にはこういう作家として売っていくぞという気概込で書いているっぽい部分になるほどなとなった。
しかし、これも現在の文庫本そこそこお高め時代にはまた話が変わってくるのかも。少し前にも本が高くなってきているというのが話題になっていたし。もうコミックス410円じゃ買えないんですか!?
しかし失敗した理由に他責多すぎん?
この何故失敗したかという話は普段聞けないもので面白かったのだけれども、一方で著者によるなぜ失敗したかという分析に違和感を覚える部分もあった。
「編集者が指摘した内容を変更したから今でも後悔している」「出版社の売り方が悪かった」「タイトルが良くなかった」など、他責的な理由付けが多いというか大半なのか気になった。いや、お前は悪くないんかい。
そのため、失敗学というタイトルから受ける分析が多そうという予想よりも、「運が悪かった」「あのとき編集の言うとおりにしていなかったら違ったかもしれない」の印象のほうが強く残ってしまったのもあるかも。人は予想と違うとアレェ? となってそのあたりが印象深くなるもんだし。
とはいえ、20作近く本を出してる作者による数冊の失敗談、そりゃあ基本的にはあたってるから編集者のせいや運のせいもあるよな、と思ったら今あんまり食えてないの? うん? いやこれもネタだよな……?
エンタメ小説の文法
本書では1章まるまる使って「読者は共感したい」「主人公に共感できなかったからつまらなかったと判定された」といった失敗分析をしてる。
著者はそれを予想外みたいな反応してるんだけれども、エンタメ小説において共感は全てではないが大事じゃないかな。
エンタメ小説の書き方の本に、よくキャラクターに短所を設定しろと出てくる。これは短所があることで自分と同じような部分のある人間だと思えてキャラクターが身近になる。これすら無いとキャラクターにただ置いていかれる物語になる気がする。
ゆーて超絶最強圧倒的主人公様というものもいるけれども、シャーロック・ホームズにはワトソンという読者側の視点があるからこそ、「ホームズやべぇな」と思える。まともな人間の視点を通して非凡な主人公を見るという構造は有効だと思うし、そうでなくとも共感の方向によっては物語の印象ってかなり変わりそう。
共感というか感情移入と言うかなんだけど、この本のなかで書かれていた『大人になりきれない』(夜明け前と彼女は知らない)に対する読者の反応がそうで、本来は主人公らを笑うOLたちのほうに感情移入して主人公らは一歩引いた客観的な目線で読んでほしかったんだけど、読者は主人公らのほうに共感・感情移入してしまったために、著者の求めていた反応とはかなり違うものが感想として出てきたんじゃないのかな。
また、他にエンタメの文法として出てきた、落ちのない物語にしてはならないという指摘にはすごくわかりがあった。これは私が純文学が苦手な理由とも重なる。純文学ってどこかふわっとしたところに帰着(実は帰着してない)して、ぶん投げ終了みたいなことが多いのが苦手。
エンタメ作品は何かしらの落ちをつけてくれるから好きなんだけど、本書で例として挙げられていた『桃の向こう』の結末は、著者の説明を読む限り「それって落ちになってないじゃん」「結局何が言いたかったの?」と思ってしまいそう。
物語の前半で提示された要素が最後にうまく回収されると気持ちいい。伏線というか、なんらかの形で解決して欲しい。ぶん投げだと伏線が回収されないように感じる。エンタメ小説にとって、そういう「落ち」の部分は本当に大事だと思った。
